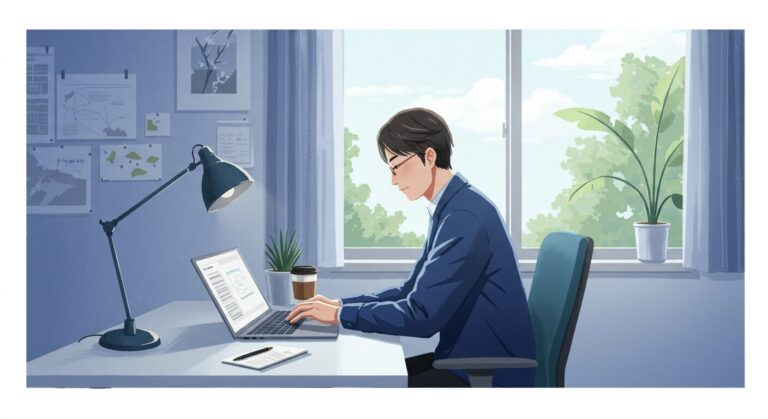エンジニアがマネジメント職になるには?年収・スキル・必須5ステップを徹底解説【2025年版

CONTENTS
「プレイヤーとしてのスキルは身についたけど、この先のキャリアはどうしよう…」
「マネジメント職に興味はあるけど、具体的に何をすればなれるのか分からない」
経験を積んだエンジニアの多くが、このようなキャリアの岐路に立ちます。AIやDXが浸透する現代において、企業は単なる技術力の高いエンジニアだけでなく、技術を理解し、チームを率いてビジネスを成功に導けるリーダーを強く求めています。
しかし、優秀なプレイヤーが必ずしも優秀なマネージャーになれるわけではありません。そこには、明確な意識改革と計画的なステップアップが必要です。
この記事では、エンジニアがマネジメント職へのキャリアアップを成功させるための具体的なロードマップを、2025年の最新データと共に徹底解説します。この記事を読めば、あなたが次に踏み出すべき一歩が明確になるはずです。
なぜ今、エンジニアがマネジメント職を目指すべきなのか?
キャリアアップを考える上で、まずは「なぜマネジメント職なのか」その理由と魅力を理解することが重要です。ここでは、データに基づいた現実的なメリットと、将来性について解説します。
年収アップの現実|データで見るマネジメント職の価値
キャリアアップの大きな動機の一つが年収でしょう。dodaの最新「平均年収ランキング」によると、その差は明らかです。
| 職種 | 全体の平均年収 | 30代の平均年収 |
|---|---|---|
| プロジェクトマネージャー | 687万円 | 711万円 |
| SE/プログラマ | 479万円 | 534万円 |
このように、マネジメント職に移行することで、年収の大幅な向上が期待できます。例えば、30代のプロジェクトマネージャーは、同年代のSE/プログラマと比較して約180万円も高い年収を得ています。
これは、個人の成果だけでなく、チームやプロジェクト全体の成果に責任を持つ役割の対価と言えるでしょう。さらに、管理職手当や賞与の増額など、給与体系そのものが優遇される傾向があります。
需要の高さと将来性|DX時代に求められるリーダー像
IPA(情報処理推進機構)の「DX白書2023」では、多くの企業がDX推進の課題として「マネジメント層のITリテラシー不足」を挙げています。そのため、現場の技術を深く理解しているエンジニア出身のマネージャーは、企業にとって喉から手が出るほど欲しい人材なのです。
例えば、技術的な実現可能性を判断しながら事業戦略を立案できる人材や、開発チームと経営層の橋渡しができる人材は、極めて希少価値が高いと言えます。この需要は、今後ますます高まっていくと予測されます。
一方で、技術だけを追求するスペシャリストの道も魅力的ですが、マネジメント職は組織への影響力が大きく、キャリアの選択肢が広がる点で優位性があります。
キャリアの広がり|技術だけではない新しいやりがい
マネジメント職は、コードを書くこととはまた違ったやりがいがあります。具体的には、以下のような魅力があります。
- メンバーの成長を支援し、チームとしての一体感を醸成する喜び
- 事業戦略に直接関わり、ビジネスを動かしているという実感
- 技術的な視点から、より大きなインパクトを組織に与えることができる
- 意思決定権を持ち、プロジェクトの方向性を自ら定められる
自分の手で創り出すことから、チームの力でより大きなものを創り出すことへ。これが、マネジメント職へのキャリアチェンジの本質です。さらに、マネジメントスキルは業界や企業を超えて通用するポータブルスキルであり、長期的なキャリア形成において強固な基盤となります。
プレイヤーからマネージャーへ|求められるスキルの劇的な変化

マネジメント職になるには、プレイヤー時代とは全く異なるスキルセットが必要です。ここでは、その変化を具体的に見ていきましょう。
思考の転換:「自分の成果」から「チームの成果」へ
最大の転換点は、評価の軸が変わることです。プレイヤーは「個人の生産性」が評価されますが、マネージャーは「チームの生産性の最大化」がミッションとなります。
そのため、自分が手を動かすのではなく、いかにメンバーに気持ちよく、効率的に働いてもらうかを考えることが仕事の中心になります。例えば、自分なら1時間で完成できるタスクでも、メンバーの成長のために任せる判断が求められます。
さらに、短期的な成果よりも、チームの長期的な成長や組織文化の醸成を優先する視点も必要です。一方で、技術的な知見は完全に捨てるのではなく、意思決定の根拠として活用し続けることが重要です。
マネジメント職に必須の3大スキル
具体的には、以下の3つのスキルを意識的に磨く必要があります。これらは相互に関連しており、バランスよく習得することが求められます。
1. ピープルマネジメントスキル:メンバーの能力を最大限に引き出す力
- 1on1ミーティング:メンバーの話を傾聴し、キャリアの壁打ち相手となる。週1回または隔週で定期的に実施し、信頼関係を構築します。
- 目標設定と評価:納得感のある目標を設定し、公正なフィードバックを行う。曖昧な評価は不信感を招くため、具体的な事実に基づいた評価が重要です。
- 心理的安全性の醸成:誰もが安心して意見を言えるチーム文化を作る。失敗を責めるのではなく、学びの機会として捉える姿勢を示しましょう。
2. プロジェクトマネジメントスキル:プロジェクトを計画通りに成功へ導く力
- タスク管理と進捗管理:WBS作成、カンバンなどでタスクを可視化し、遅延を防ぐ。例えば、JiraやAsanaなどのツールを活用して、リアルタイムで進捗を把握します。
- リスク管理:潜在的なリスクを事前に洗い出し、対策を講じる。技術的負債や人員不足などを早期に発見し、エスカレーションすることが重要です。
- ステークホルダー調整:関係各所と円滑なコミュニケーションを取り、合意形成を図る。開発チーム、営業、経営層など、異なる立場の人々の利害を調整します。
3. プロダクトマネジメントスキル:「何を作るか」を定義し、ビジネス価値を高める力
- 課題発見と要件定義:ユーザーやビジネスサイドの課題を正確に捉え、システム要件に落とし込む。技術視点だけでなく、ビジネス視点での優先順位付けが求められます。
- 意思決定:技術選定や仕様決定において、トレードオフを考慮し最適な判断を下す。完璧な解決策は存在しないため、制約条件の中でベストな選択をする力が必要です。
【5ステップ】エンジニアがマネジメント職になるための実践ロードマップ
では、これらのスキルを身につけ、マネジメント職になるには、具体的に何をすれば良いのでしょうか。ここでは、明日から始められる5つのステップを紹介します。
Step1. 自己分析:「なりたいマネージャー像」を明確にする
まずは、自分がどんなマネージャーになりたいのかを言語化することから始めましょう。「技術でチームを引っ張るテックリード」なのか、「メンバーの成長支援に注力するエンジニアリングマネージャー」なのか。
例えば、尊敬する上司や、理想のリーダー像を参考に、自分の目指す方向性を定めます。さらに、自分の強みと弱みを客観的に分析し、どの領域で価値を発揮できるかを見極めることが重要です。
一方で、マネジメント職が本当に自分に合っているのかを見極めるために、既存のマネージャーに話を聞いたり、一時的にリーダー役を経験させてもらったりすることも有効です。
Step2. 基礎知識のインプット:書籍や講座で体系的に学ぶ
自己流で始める前に、マネジメントの「型」を学ぶことが重要です。まずは以下のテーマに関する書籍を1〜2冊読んでみましょう。
- リーダーシップ論:『サーバント・リーダーシップ』『HIGH OUTPUT MANAGEMENT』など
- プロジェクト管理:『アジャイルサムライ』や、PMIが提唱するPMBOKの基礎知識など
- チームビルディング:『Team Geek』『心理的安全性』『ザ・ゴール』など
さらに、Udemyなどのオンライン講座を活用するのも効果的です。例えば、「1on1ミーティングの進め方」や「OKRの設定方法」など、実践的なスキルを短期間で習得できます。
したがって、理論と実践の両面から学ぶことで、マネジメントの全体像を掴むことができます。一方で、知識だけでは不十分なため、必ず実践と組み合わせることが重要です。
Step3. 小さなチームでの実践経験:「プレマネージャー」を経験する
インプットの次は、実践です。いきなりマネージャーになるのではなく、まずは3〜5人程度の小規模チームのリーダーやテックリードを経験させてもらうよう、上司に働きかけてみましょう。
ここで、進捗管理、タスクの割り振り、メンバーからの相談対応といった「プレマネージャー」としての経験を積むことが、最も効果的なトレーニングになります。例えば、新人のオンボーディング担当や、小規模な改善プロジェクトのリーダーなどが良い機会です。
さらに、失敗しても大きな影響が出ない範囲で挑戦できるため、安心して試行錯誤ができます。この経験を通じて、自分の適性やマネジメントスタイルを見極めることができます。
Step4. 1on1とフィードバックの練習
マネジメントの核は、メンバーとの対話です。まずは後輩やチームメンバーと、業務として1on1ミーティングを始めてみましょう。ポイントは「自分が話す」のではなく「相手の話を聴く」ことに徹することです。
例えば、相手の課題やキャリアの悩みを引き出し、壁打ち相手になる練習を重ねましょう。最初は30分程度から始め、徐々に質問力や傾聴力を磨いていきます。
さらに、ポジティブなフィードバックと建設的な改善提案をバランスよく伝える練習も重要です。一方で、フィードバックは具体的な事実に基づいて行い、人格否定にならないよう注意が必要です。
Step5. 資格や実績でキャリアを客観的に証明する
ある程度の経験を積んだら、そのスキルを社内外に示すために資格取得を目指すのも有効な手段です。代表的な資格には以下があります。
- プロジェクトマネージャ試験(情報処理技術者試験):国家資格として認知度が高く、日本国内での評価が高い
- PMP (Project Management Professional):国際的に通用する資格で、外資系企業での評価が特に高い
- 認定スクラムマスター(CSM):アジャイル開発のファシリテーターとしてのスキルを証明
これらの資格は、あなたのマネジメントスキルを客観的に証明し、昇進や転職の際に大きな武器となります。したがって、キャリアの節目で取得を検討することをおすすめします。
マネジメント職を目指す際の注意点とよくある失敗
マネジメント職への転身は魅力的ですが、注意すべきポイントもあります。ここでは、よくある失敗パターンと対策を紹介します。
失敗パターン1:プレイヤーとしての仕事を手放せない
技術者として優秀だったエンジニアほど、「自分でやった方が早い」という罠に陥りがちです。しかし、これではチームの成長を阻害してしまいます。
そのため、意識的に「任せる」練習をし、メンバーが失敗する余地を残すことが重要です。一方で、完全に技術から離れる必要はなく、技術的な判断が必要な場面では積極的に関与すべきです。
失敗パターン2:コミュニケーション不足による信頼の喪失
マネージャーになると、会議や調整業務が増え、メンバーとの対話時間が減りがちです。例えば、定期的な1on1を疎かにすると、メンバーの悩みや不満を見逃してしまいます。
したがって、どんなに忙しくても、メンバーとのコミュニケーション時間は最優先で確保する必要があります。さらに、オープンドアポリシーを実践し、いつでも相談できる雰囲気を作ることも大切です。
失敗パターン3:結果を急ぎすぎて短期思考に陥る
マネージャーとして成果を出そうと焦るあまり、短期的な数字ばかりを追いかけてしまうケースがあります。しかし、チームの成長や文化の醸成には時間がかかります。
一方で、長期的な視点を持ちながらも、小さな成功体験を積み重ねることで、チームのモチベーションを維持することが重要です。例えば、四半期ごとに振り返りを行い、改善を続ける姿勢が求められます。
まとめ:マネジメントは新たな価値を創造するスキルである

エンジニアがマネジメント職へのキャリアを歩むことは、コーディングという武器を手放すことではありません。むしろ、「チーム」という新しい武器を手に入れ、より大きな課題解決に挑むための進化です。
プレイヤーとしての現場経験は、あなたのマネージャーとしてのキャリアにおいて、何物にも代えがたい財産となります。技術がわかるからこそ、的確な意思決定ができ、メンバーから信頼されるリーダーになれるのです。
さらに、実務直結の社内研修や伴走型支援を活用すれば、プレイヤーから「SE(上流工程)」への移行は加速します。例えば、検索意図設計・E-E-A-T強化・キーワードマップ活用・SERP分析・リライト運用・KPI設計までを体系化した研修と、実案件OJT・1on1サポートを組み合わせることで、受講後にCVR改善を主導し、設計レビューや要件定義の場でリードできるようになった事例が生まれています。
この記事で紹介した5つのステップを参考に、まずは「Step1. 自己分析」と「Step2. 基礎知識のインプット」から始めてみてください。あなたの主体的な一歩が、キャリアの新たな扉を開く鍵となるはずです。
そして、長期的な視点を持ち、日々の小さな実践を積み重ねることが成功への近道です。焦らず、着実に、自分らしいマネジメントスタイルを確立していきましょう。
ドライブラインなら、SEからの次の一歩も“現場で”試せます
ドライブラインではSEまでの育成を前提に、適性と実績に応じてPL/PMとして参画できる案件も用意しています。カリキュラムでPL/PM養成をうたうものではありませんが、社内の評価基準に沿ってステップを可視化し、配属後は先輩リーダーのレビュー体制でチャレンジの機会を提供します。
まずはSEで上流を担当
要件定義・基本設計・進行管理を通じて、リーダーの土台を構築。
評価に応じてPL案件へ
小規模チームのWBS/リスク管理を実務で経験できます。
PM補佐で意思決定を学習
見積・進捗会議・ステークホルダー調整を現場で習得。
ロールモデル多数
社内の先輩SEがPL/PM案件へ挑戦した事例が蓄積。
「SEで実績を作り、次はPL/PMに挑戦したい」という方は、採用ページにてご確認ください。