ITエンジニアの休日・残業の実態【2024年最新データで見るリアル】
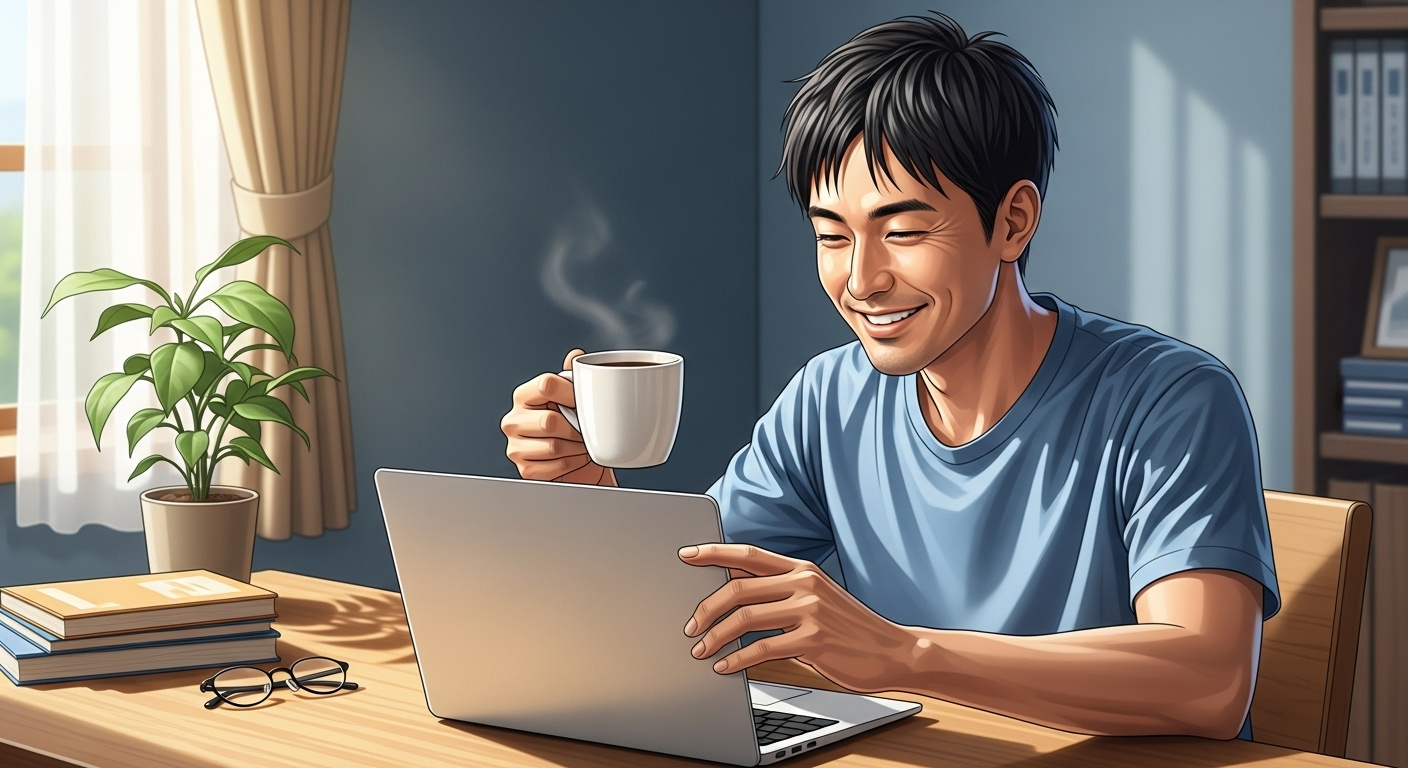
CONTENTS
IT業界ではリモートワークが定着し、かつてないほど柔軟な働き方が広がっています。
しかし一方で、「休日もついSlackを開いてしまう」「気づけば自宅で作業をしてしまっている」といった声が後を絶ちません。
そのため、エンジニアが心身ともに健全に休む環境をいかに整えるかが、長期的なキャリアを築く上で極めて重要なテーマとなっています。本記事では、公的機関が公表した2024年時点の最新データをもとにITエンジニアの休日のリアルな実態を解き明かし、理想のワークライフバランスを保つための具体的な方法を徹底解説します。
年間休日は平均123日!しかし「休日の質」に潜む課題
厚生労働省が発表した「令和5年就労条件総合調査」によると、ITエンジニアが多く含まれる「情報通信業」の年間休日総数は平均123.0日でした。これは全産業平均の117.1日を約6日も上回る数字であり、カレンダー通りの休日を確保しやすい恵まれた業界であると言えます。
しかし、問題は「休日の質」にあります。数字の上では休めていても、精神的には仕事から解放されていない「なんちゃって休日」を過ごしているエンジニアは少なくありません。例えば、プロジェクトの納期が迫ると休日出勤が発生したり、システム障害に備えて常に待機(オンコール)状態でなければならなかったりするケースです。
したがって、単純な日数だけでは働きやすさを測れないのが実情です。さらに、リモートワークの普及がこの問題に拍車をかけています。総務省の調査では情報通信業のテレワーク実施率が58.3%と突出して高い一方、「通勤時間がなくなったことで公私の境界が曖昧になった」と感じる人が増加しています。
一方で、自宅が職場と直結しているため、オンとオフの切り替えが以前より難しくなっているのです。このような状況下では、意識的に休息をデザインする必要性が高まっています。
残業時間は減少傾向も、職種・企業規模による格差は依然として大きい
次に、残業時間を見ていきましょう。大手転職サービスdodaの「平均残業時間ランキング(2023年版)」によれば、「IT/通信系エンジニア」の残業時間は月平均19.6時間です。数年前の調査と比較すると着実に減少しており、業界全体の労働環境が改善に向かっていることが伺えます。
しかし、この数字はあくまで平均値です。職種や所属する企業の文化、規模によって実態は大きく異なります。例えば、以下のような違いが見られます。
- 大手Webサービス・社内SE:自社サービスを扱うため比較的スケジュール調整がしやすく、残業も少ない傾向にあります。有給取得率も高く、ワークライフバランスを重視する文化が根付いています。
- SIer・受託開発:クライアントの納期が絶対であるため、プロジェクトの終盤(いわゆるデスマーチ)には残業や休日出勤が集中しがちです。
- スタートアップ:少数精鋭で開発スピードを重視するため、一人当たりの業務範囲が広く、突発的な対応も多いため労働時間が長くなる傾向があります。
- インフラ・運用保守:24時間365日の安定稼働が求められるため、夜間や休日の障害対応は避けられず、シフト勤務や待機日が多くなりがちです。
さらに、この格差は年次有給休暇の取得率にも表れています。前述の厚労省調査では、企業規模1,000人以上の大企業(情報通信業)の有給取得率が70.2%であるのに対し、30~99人の中小企業では60.9%と約10ポイントもの差が開いています。
したがって、転職を考える際は業界の平均値だけでなく、その企業のリアルな働き方を多角的に調べることが不可欠です。面接時に具体的な残業時間や有給取得率を確認することが重要です。
イマドキのエンジニアはどう過ごしてる?休日のリアルな過ごし方3選
多忙な毎日を送るITエンジニアは、貴重な休日をどのように過ごしているのでしょうか。ここでは代表的な3つの過ごし方を紹介します。
1. スキルアップや副業で未来に投資する
まず、最も多いのが休日を自己投資の時間に充てるパターンです。技術の進化が速いIT業界では、常に新しい知識を学び続ける姿勢が求められます。そのため、多くのエンジニアが休日を活用して自身の市場価値を高めています。
例えば、Udemyのようなオンライン学習サービスで、PythonによるAI開発やAWS/GCPといったクラウド技術、ReactやVue.jsなどのモダンなフロントエンド技術を学ぶのが主流です。さらに、学んだ知識を活かして技術ブログを執筆したり、副業で小規模な案件を受けたりすることで、実践的なスキルと収入を同時に得ている人も増えています。
一方で、過度な自己投資は逆効果になる場合もあります。したがって、学習時間と休息時間のバランスを意識することが重要です。
2. デジタルデトックスで「仕事脳」を強制オフする
「休日くらいはPCやスマホから離れたい」と考え、意識的にデジタルデトックスを実践するエンジニアも急増しています。平日、長時間モニターと向き合っているからこそ、休日は五感を使ってリフレッシュすることの重要性が再認識されているのです。
例えば、キャンプや登山、釣りといったアウトドア活動、ジムでの筋トレ、サウナ、カフェ巡りなど、物理的にデジタルデバイスから離れられる趣味が人気です。このように、意図的に「仕事脳」を休ませる時間を作ることで、精神的な疲労を回復させ、翌週の創造性や集中力を高めることができます。
さらに、デジタルデトックスは睡眠の質向上にも効果的です。したがって、週末の夜だけでもスマホを寝室に持ち込まない習慣を始めてみることをおすすめします。
3. 趣味やコミュニティ活動で視野を広げる
仕事とは全く関係のない趣味に没頭することも、優れたリフレッシュ方法です。音楽、ゲーム、写真、料理、ボードゲームなど、自分の「好き」を追求する時間は、仕事のストレスを忘れさせてくれるだけでなく、新たな発想の源泉にもなり得ます。
また、技術カンファレンスや勉強会にボランティアスタッフとして参加するなど、社外のコミュニティ活動を通じて人脈を広げることも、キャリアに良い影響を与えます。例えば、OSS(オープンソースソフトウェア)への貢献活動は、スキルアップと社会貢献を同時に実現できる魅力的な選択肢です。
したがって、休日を多角的なインプットとアウトプットの機会と捉えることが、豊かなエンジニアライフにつながると言えるでしょう。
【明日からできる】ワークライフバランスを劇的に改善する5つの行動
ここまで見てきた課題を踏まえ、心から休める休日を手に入れるための具体的なアクションプランを「個人編」と「組織編」に分けて5つ紹介します。
1. 【個人編】時間の使い方を「データ化」してボトルネックを発見する
まず個人でできる最も効果的な一歩は、「時間の使い方をデータ化する」ことです。そのためには、Toggl Trackのようなタイムトラッキングツールを使い、1週間の業務内容(コーディング、会議、調査など)を記録してみましょう。
これにより、「集中力が高い時間帯」や「無駄になっている時間」が客観的に可視化され、どこを改善すればよいかが一目瞭然になります。例えば、午前中の集中力が高い時間を会議に費やしていることに気づけば、スケジュールの調整が可能になります。
また、タスク管理においては「やることリスト(To-Do List)」だけでなく、「やらないことリスト(Not-To-Do List)」を作成するのも有効です。例えば、「午前中はSlackをチェックしない」「目的のないネットサーフィンはしない」といったルールを決めることで、集中力を維持し、不要なタスクから自分を守ることができます。
2. 【個人編】仕事の終わりを告げる「終了儀式」を習慣化する
リモートワークで曖昧になったオンとオフの境界線を再び明確にするためには、「終了儀式(シャットダウン・リチュアル)」が効果的です。これは、一日の仕事の終わりに必ず行う決まった行動のことです。
例えば、「PCをシャットダウンし、デスク周りを片付ける」「今日の成果を3つだけ書き出す」「仕事用のチャットアプリをすべて閉じる」「散歩に出かける」など、何でも構いません。さらに、着替えや軽い運動を組み合わせることで、より効果的な切り替えが可能になります。
この儀式を習慣化することで、脳に「ここからはプライベートな時間だ」と明確なシグナルを送り、仕事モードからスムーズに切り替えることができます。したがって、自分に合った終了儀式を見つけることが、休日の質を高める第一歩となります。
3. 【組織編】心理的安全性を高め「休む=悪」の文化をなくす
一方で、個人の努力だけでは限界があります。組織としての取り組みも不可欠です。特に重要なのが、休暇を取得することに罪悪感を感じさせない「心理的安全性」の高いチーム文化を醸成することです。
例えば、マネージャーが率先して長期休暇を取得したり、チームメンバーの休日を尊重する発言を心がけたりするだけでも、雰囲気は大きく変わります。さらに、チーム内で休暇スケジュールを共有カレンダーなどで可視化し、お互いがサポートし合える体制を整えることも重要です。
したがって、「休むことは、良い仕事をするための重要な責任である」という認識をチーム全体で共有しましょう。この文化が定着すれば、離職率の低下や生産性向上にもつながります。
4. 【組織編】Googleも実践する「No Meeting Day」の導入
世界的な大企業も、生産性と休息の両立のために工夫を凝らしています。例えば、GoogleやFacebook(Meta)では、週に1日、社内会議を一切禁止する「No Meeting Day」を導入しています。
これにより、エンジニアはまとまった集中時間を確保でき、コーディングや設計などの創造的な作業に没頭できます。この取り組みは、不要な会議の削減につながり、結果として時間外労働の抑制と業務効率の向上に大きく貢献すると報告されています。
さらに、国内でも同様の制度を導入する企業が増えており、組織改革の有効な一手として注目されています。したがって、自社でも導入を検討する価値は十分にあります。
5. 【組織編】法規制を遵守し、客観的データで勤怠を管理する
企業は働き方改革関連法で定められたルールを遵守する義務があります。具体的には、「時間外労働の上限規制(原則月45時間・年360時間)」や「年5日の年次有給休暇の取得義務化」です。
これらの法的要件を満たすためにも、勤怠管理システムを導入し、全従業員の労働時間を客観的なデータで正確に把握することが大前提となります。例えば、クラウド型勤怠管理システムを活用すれば、リモートワーク環境でも正確な労働時間の把握が可能です。
一方で、データを取得するだけでなく、定期的に分析し、問題がある部署やプロジェクトには早期に介入することが重要です。したがって、人事部門とマネージャーが連携して、働き方の改善に取り組む体制を整えましょう。
休日を充実させるための追加テクニック
基本的な改善策に加えて、さらに休日の質を高めるためのテクニックを紹介します。
マインドフルネスと瞑想の活用
近年、IT業界で注目されているのがマインドフルネスと瞑想です。例えば、GoogleやAppleなどの大手企業では、社員向けに瞑想プログラムを提供しています。
これらの実践により、ストレス軽減や集中力向上、創造性の向上が期待できます。さらに、1日10分程度の短時間から始められるため、忙しいエンジニアでも無理なく継続できます。
したがって、休日の朝に瞑想の時間を設けることで、一日をより充実したものにできるでしょう。HeadspaceやCalmといったアプリを活用すれば、初心者でも簡単に始められます。
休暇の「質」を高める事前計画
休日を有意義に過ごすためには、事前の計画が重要です。例えば、週の初めに次の休日の過ごし方を具体的にイメージしておくことで、休日当日に「何をしようか」と悩む時間を削減できます。
また、長期休暇を取る際は、完全なデジタルデトックスを実現するために、業務の引き継ぎを徹底し、緊急連絡先を限定しておくことが大切です。一方で、休暇明けのキャッチアップ時間も考慮に入れたスケジュール調整が必要です。
さらに、「攻めの休暇」として、旅行やイベント参加など積極的な活動と、「守りの休暇」として、家でゆっくり過ごす時間のバランスを取ることも重要です。
まとめ:主体的に「休み」をデザインし、豊かなエンジニアライフを

本記事では、2024年時点の最新データに基づき、ITエンジニアの休日事情とワークライフバランス改善のための具体的なヒントを紹介しました。平均休日数は他産業より多いという恵まれた環境にあるものの、その裏側では精神的に休めていない「なんちゃって休日」が大きな課題となっています。
したがって、これからのエンジニアには、会社から与えられた休日をただ過ごすのではなく、自らの手で「最高の休息」を主体的にデザインしていく姿勢が求められます。個人レベルでの時間管理と、組織レベルでの文化醸成、その両輪が揃って初めて、真のワークライフバランスは実現します。
今日からできる小さな一歩として、まずは「次の週末、半日だけでも完全に仕事用のデバイスの電源をオフにする」ことから始めてみませんか。休むことは、決して怠慢ではなく、最高のパフォーマンスを発揮するための最も重要な戦略なのです。




